3DCGはマシンパワーを要求する分野です。
よって、3DCG用PCのスペックは非常に重要です。
つまり、適当にPCを選んでしまうと後悔することになります。
そうしたわけで、3DCGのためのPCは、いろいろとカスタマイズできるBTO(Build To Order)パソコンが最適です。
BTOパソコンとは自分好みにカスタマイズして受注生産するパソコンのことです。
もちろん、自作PCでも構いませんが、すべて自己責任になってしまうことは覚悟しましょう。
特に、仕事で使う場合にはマシントラブルは命取りになります。
そうした意味でもBTOパソコンが最適です。
また、ゲーミングPCも高性能です。よって、3DCG用のクリエイティブ用途のPCとどう違うのかという問題もあります。ゲーミングPCでももちろん十分ですが、必ずしも十分ではないとも言えます。そのあたりについても触れます。
前提条件として3DCGアプリケーションはMayaまたはBlenderを使用することとします(両方使用してもかまいません)。さらに、Unreal Engine 5 も使用することとして話をすすめます。
ちなみに、このページで紹介するPCはWQHD(2560×1440)以上の解像度(広い画面)で、快適に作業できるPCを主なターゲットとしています。
とにかく、早くおすすめのPCを知りたい方は「こちら」から進んでください。
しかし、これから3DCGをはじめるにあたって、まずは安価なモノを購入してスタートしたい場合は「こちら」におすすめのPCを2つピックアップしてあります。

なぜこれらのアプリケーションを選ぶのかについては過去の記事を御覧ください。

ここでは、簡単に説明しておきます。
Mayaはハリウッド映画やビデオゲームの開発で使用されている業界スタンダードの3DCGソフトウェアです。有名な映画やゲームではほとんどこのMayaが使用されている(実際はMayaだけでなく他のものも使われています)と考えてください。つまり、将来ゲームや映画を作りたいと思っている人はMayaを選びましょう(Mayaの場合は、特に大人数のチームでの制作に向いています)。
次にBlenderは無料で使えるオープンソースソフトウェアです。しかも、いわゆるGAFAM(Google, Amazon, Facebook(現Meta), Apple, Microsoft)がBlender Development Fundという開発基金の後援になっています。また、GAFAMだけでなく、NVIDIA、AMD、intel、Adobe等名だたる企業が参加しています。この事実だけでも最も勢いのある3DCGアプリケーションであることがわかるでしょう。つまり、無料ですぐに3DCGをはじめたい人はBlenderを選びましょう(仕事の場合でも個人や少人数で完結するプロジェクトの場合、Blenderはとても有用です)。
Unreal Engineは、フォートナイトで有名なEpic Gamesのゲームエンジンです。フォートナイトだけでなく、世界中のハイエンドのビデオゲームの開発で使われています。Unreal Engineで作ったものが相当な売上がないかぎり(個人レベルで使用する場合はほぼ無料)はで使用できます。また、リアルタイムレンダリングが非常に優れているので映像分野でも使用されるようになりました(ゲームに興味がない人でも注目すべきです)。ゲームエンジンという特性上、Unreal Engineは、MayaやBlenderといったDCC(Digital Content Creation)ツールと一緒に使うことで本領を発揮します。よって、MayaかBlenderがある程度使えるようになってから取り組めば良いです。
このようにおすすめの3つの中の2つが無料で使用できます。
よって、ソフトウェア側にはお金を使わずに3DCGを始めることができます(Mayaの場合は将来、特にゲームや映画といった大人数のプロジェクトを仕事としてやりたい人向けです)。
3DCGに適したパソコン(PC)さえあれば誰でもすぐに始めることが出来ます。
本当に非常に良い時代になったものです。
では一体どんなPC用意したらよいのでしょうか。
結論は、「WindowsのデスクトップでNVIDIAのGeforceRTXのグラフィックカードを搭載したもの」です。
ちなみに「グラフィックカード、ビデオカード、グラフィックボード(グラボ)」と呼び方はいろいろありますが、同じものです。Googleで調べた結果「グラフィックカード」が最も検索結果が多かったので「グラフィックカード」を使用しています。
個人的なイメージでは、「ビデオカード」は古く(Windows95以前のDOS/Vパソコン)からPCに親しんでいる人。「グラフィックカード」は「ビデオカード」という言い方はさすがに古臭いと思っている人。「グラフィックボード(グラボ)」は比較的最近(グラフィックカードが分厚くなってから)の人です。
私の場合は、うっかり「ビデオカード」と言ってしまうことがたまにあります。略して言うときは「グラボ」が多いです。
M4 ProのMacBook ProとM4 MacBook Air、そしてWindowsはRyzen 9 7900とGeForce RTX4070 SUPERのデスクトップ、そしてノートPCのintel Core i7とGeForce RTX 3070での検証です。
非常に参考になるので、時間がある方は観てみてください。
結論としては、やはりWindowsです。
ただし、Apple SiliconのM4チップのCPU性能が非常に高いことが良くわかります。
GPUについては、M4チップのものは、CPUと一体型なので、やはり限界があります。
ただし、ちょっと前までは、Macで3DCGというのは論外みたいな感じでした。しかし、ここ最近のApple Siliconの進化は凄まじく、またMaya, Blender, HoudeniといったアプリケーションもApple Siliconへのネイティブ対応がほぼ完了したといっても良い状況にまでなりました。
よって、「ノートPCで3DCG(サブマシンとして)をやるならMacもおおいにアリ」です。
しかし、メインマシンということならば、NVIDIAのグラフィックカードを使えるWindows PCに大きなアドバンテージがあるのは事実です。
まずは、デスクトップのメインマシンを用意しましょう。
Macもありな状況になりつつありますが、まだ時期尚早(CPUに関しては、Macのほうが速いといっても良いのですが、GPUに関してはNVIDIAには敵いません)といったところです。さらに、Unreal Engine 5 のことも考えるとWindowsを強くおすすめします。
こちらの動画は、RTX5090とM4 MAXの比較です。
本来比較出来るものではないのですが、どちらも非常に高額で、3DCGのためならばRTX5090を購入したほうが幸せになれます。
私はMayaを20年程度使用しています。そのため、我が家では何台ものBTOパソコンが世代交代してきました。その経験を踏まえ、MayaやBlender(それ以外のDCCツールも)、そしてUnreal Engine 5 を使う上でどのようなPCが良いのか考えて行きます。
特にMayaやBlendrといったDCCツールを使用するためにBTOパソコンを選ぶ場合はより参考になると思います。
PCを選ぶ際のスペック等の話は、PCに詳しくない人にとっては専門用語ばかりで難しいと感じるはずです。
とにかく、どのPCを買えばいいのか具体的に早く知りたい方は「3DCGをはじめるならこれを買え!《PC編》」を御覧ください。予算別におすすめPCをピックアップしています。
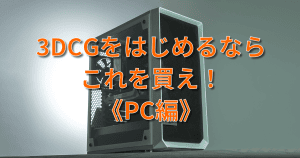
3DCG向けPCのスペック【Maya, Blender, Unreal Engine】
想定する3DCG環境は「Maya、またはBlender、そしてUnreal Engine 5」です。
主にMaya向けの3DCG用PCということでお話します(BlenderはMayaが動く環境ならば問題ないと判断したため)。Mayaを使用するには費用がかかります。せっかくBTOしたのにMayaが動かなかったというリスクは避けたいからです。
そして、Unreal Engine 5(UE5) についてです。
現在ではMayaが求めるスペックよりもUE5が要求するもののほうが厳しいです。
UE5をどれだけ使いたいかによって「どれくらいの性能のPCが必要か?」が決まります。
MayaやBlenderだけでモデリングからレンダリングまでして終わりならばそれほどのスペックは必要としません。
もちろん、大規模なシミュレーションを必要とするエフェクトを作りたいといった場合は別です。そうした場合はハイエンドのものを揃えなければなりません。
ゲーミングPCとの違い
自作PCやBTOパソコンに詳しいかたはゲーミングPCとどう違うのかが気になるところだと思います。
ゲーミングPCとの一番の違いはメモリを多く積むことです。
昔はQuadroといったGeForceと同じチップを使いながらも高価なワークステーション用のグラフィックカードを使用する必要がありました。そうしないとMayaを使用した場合、表示上の不具合が起こることがありました。
そうした訳でQuadroというワークステーション用のグラフィックカードを使用することが推奨されていましたが、今ではUureal EngineのおかげもあってGeForceのRTXを使えば間違いない状況になりました。
ただし、グラフィックスドライバにはクリエイティブ用途の「Studioドライバ」を使用することになります。
そういったわけでUnreal Engineに感謝しながら予算に合わせてGeForce RTXのグラフィックカードを選びましょう。
もし、今手元にゲーミングPC(GeForce RTXの)があるようでしたら、主にメモリを追加するなどするだけでも十分な場合もあるでしょう。そういった場合はまずは手元にあるゲーミングPCで3DCGを始めてみてください。
3DCG向けPCの特徴
- OSはWindowsのProバージョンを使ったほうが無難。
- メモリはゲーミングPCよりも多く積む(できれば64GB以上、最低32GB)。
- グラフィックカードはNVIDIAのものを選ぶ。GeForce RTXが良い。
- GeForceの「Studioドライバ」を使う。
- グラフィックカードはメモリ容量が大きいもの(出来れば16GB以上)を選ぶ。
- CPUはコア数が多いものを選ぶ。
- 作業領域が狭いと使いづらいのでモニターは大きめ(27インチ以上、マルチモニターも推奨)を選ぶ。
Windowsは「Pro」バージョンを選ぶ
Windowsの「home」と「Pro」の違いは、機能面での違いはもちろんのこと、セキュリティー面であったり、「Home」ではドメインに参加できないといった問題があります。これらの問題を考えても「Pro」を選んでおけば間違いないと言えます。
さらに、最大のメモリ容量が「Pro」では2TBであるのに対し、「Home」は、128GBまでしかありません。現状では128GBまであれば十分ですが、過去のPCのハードウェアのメモリ搭載量の増え具合からすると、将来的に不安がないわけではありません。思ったよりも早くメモリ256GB時代がやってくるでしょう。
Mayaに関しては、Maya2020の動作環境まではWindows10Professionalという記述がありましたが、Maya2022の動作環境以降からはProfessionalの記述はありません。また、Maya2023の動作環境からはWindows11も対象となっています。よって、今から購入する場合はProでなくても良いのかもしれませんが、20年近くMayaを使っている者からするとProを選ぶ方が無難でしょう(1万円弱高くなってしまいますが、逆に言えば1万円弱節約してまで「Home」にするメリットはありません)。
そして、Windows10か11かの問題に関しては、サポートがなくなってしまうのが時間の問題なので今から買うのであればWindows11をおすすめします。
結論として、今から選択するのであればOSは、「Windows11 Pro」ということになります。
そういったわけで、私は「Windows 2000」以降は、Proバージョンしか購入したことがありません。
よって、私の経験上使ったことがないということからも「Home」をおすすめすることはできません。
メモリは理想は64GB以上、最低でも32GB以上
メモリに関してはUnreal Engine 5でゲームを開発するための合理的なガイドラインにしたがって「64GB」以上が望ましいです。
UNREAL ENGINE 5 ハードウェアおよびソフトウェアの仕様 より
- Windows 10 64-bit (Version 20H2)
- 64 GB RAM
- 256 GB SSD (OS Drive)
- 2 TB SSD (Data Drive)
- NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER
- Xoreax Incredibuild (Dev Tools Package)
- Six-Core Xeon E5-2643 @ 3.4GHz
とはいっても64GBは金銭的に厳しい場合は少なくとも32GBは欲しいところです。
「Unreal Engine 5は結構です。触りません」という場合ならば16GBでもいけるかもしれませんがおすすめはしません(金銭的に余裕はないけれど、とにかく3DCGをやってみたい場合にはありです。3DCGができる環境がないのでは何もはじまりません)。
メモリスロットの空きを作っておいて、あとから増設して64GBまで(またはそれ以上)増やせるようにしておきましょう。
グラフィックカードに関してはGeforceRTXの5000番代を予算に合わせて選びましょう。
できることならばグラフィックカードのメモリも多めのもの(8GBだと心もとないので、出来れば16GB以上)をおすすめします。
BTOパソコンとは関係のない話ではありますが、モニターに関しては作業領域はできるだけ広くとりたいので大きいものやマルチモニターを推奨します。FPSのようにモニターが広すぎる不利になることは絶対にありません。さらに、できれば目が疲れにくいものが望ましいです。
とはいえ、使えるモニターを持っているのであれば、それを使ってそのぶんBTOパソコンのほうにコストをかけましょう。
CPUは「intel」か「AMD」か?
結論から言うと、「どっちでもOK!(ちなみに、2024年はAMD一択状況でした)」。
※2024年12月現在、「0x12B」というマイクロコードを適応することで、intelの13,14世代CPUの不具合問題は解決されました。
intelの13(core i9 13900、core i7 13700、core i5 13500等),14世代(core i9 14900、 core i7 14700、 core i5 14500等)世代CPUの不具合問題があったことから、これらのCPUは安価に入手できることがありますが、PCに詳しい人以外にはおすすめは出来ません。
intelのCPUを選ぶ場合は、core Ultraシリーズから選ぶようにしましょう(ちなみに、12世代(12X00)シリーズには不具合はありませんが、わざわざ古いものを選ぶ必要はないでしょう)。
AMDの場合は、特に世代を意識する必要はありませんが、当然のことながら新しいもののほうがパフォーマンスが良いです。
Ryzen CPUには、末尾にX3Dがついた、ゲーミング性能最強と言われるCPUがあります。3D V-Cashとういものが搭載されているために、少し割高になっています。しかし、3DCG用途では、X3Dに拘る必要はありません。例えばRyzen 7 9800X3DとRyzen 9 9900XというCPUがあるのですが、3DCG用途としては、コア数が多いRyzen 9 9900Xのほうがおすすめです。同じCPUで末尾にX3Dがついたものも存在し、もちろんX3Dがついたもののほうが性能は上ですが、コストを抑えたい場合は、X3Dではなく、Xのほうを選びましょう。
そういった意味では、ほとんどの人にとっては、intelのCPUでも、AMDのCPUでもどちらでもかまいません。
ただ、現状では「AMDのCPUのほうが売れている」ので、世の中の評価を気にする人はAMDを選んでおいたほうが無難です(ちょっと前までとは全く逆の状況なので、驚かれてる人もいるでしょう)。
とはいえ、今はCPUよりもGPUの重要性が高まっている状況です。
以前は、PCを選ぶ際には、最初にCPUを選んでいたのですが、今は最初にGPUを選ぶ時代になりました。GPUを選んだ後に、価格面やオプションを見てintelにするかAMDにするか判断すればよいでしょう。
ただし、CPUは心臓部分なので最重要パーツであることは今も昔もかわりません。
コア数はレンダリングのスピード(CPUレンダリングの場合)とシミュレーションのスピードに関わってきます。たくさんレンダリングしたい人(GPUレンダリングのほうがスピードは速いですが、動画にする場合はノイズの関係でCPUレンダリングのほうが好ましいです)や、シミュレーションをたくさん試したい人は、core Ultra 9、またはRyzen 9を検討しましょう。
せっかく良いグラフィックカードを使っていてもCPUもそれなりの性能のものを使用しないと、能力を発揮しきれません。特に3DCGの場合は、CPUでレンダリングすることになる(GPUだとノイズの問題で動画にするとチラついてしまう)ので、CPUは重要です。
メモリ4枚挿し問題
intelとAMDのCPU両方とも問題点として、メモリを4枚挿した場合(32GB*4=128GBなど)、メモリのクロックスピードが落ちてしまうという仕様上の問題があります。
ただし、そこまで高スペックのPCを購入する人は少ないと思うので、「そういうこともあるのか」程度にとどめておきましょう。
「32GB*2の64GB」と「64GB*2の128GB」のメモリのPCでは、明らかに128GBのメモリを搭載したPCのほうが性能は上です。予算が許すならば迷わず128GBのほうを選びましょう。
ここで注意したいのは、「16GB*4の64GB」という構成のPCを稀に見かけることがあります。
こういった構成のものは選ばないのが懸命です。
同じ64GBのPCならば、「32GB*2の64GB」のものを選びましょう。
これがどうしても嫌だという人は、Sycomで48GB*2の96GB構成が選べるPCも存在します。
グラフィックカードはNVIDIA1択
グラフィックカードの分野ではNVIDIA一強なのは昔から変わっていません。
Mayaの場合はArnoldでNVIDIAのGPUでGPUレンダリングができます。
RTX 4090が相手では…。せめてCore i9のCPUと勝負してほしかったところですが、GPUレンダリングの速さを知るには十分すぎます。
BlenderでもGPUのほうが速いことがわかります。この動画を見る限りでは、「3DCGはMacよりもWindowsだということがわかります。」
Blenderの場合はAMDのRadeonや、Apple siliconのMetalでもGPUレンダリングができますが、やはりNVIDIAのGeForce RTXがベストチョイスです。
オンボードグラフィックスは必要か?
普段はグラフィックスカードを使うのでマザーボードに内蔵されているオンボードグラフィックスは使いません。
そう考えると少しでも安く済ませるためにはオンボードグラフィックスなしのモデルのほうがベターです。
しかし、私にはグラフィックスカードが壊れた経験があります。
そのときは内蔵グラフィックスカードがあったことでPCを起動してグラフィックスカードが故障したという事実を突き止めることが出来ました。
私の経験から、「もしもの時のためにオンボードグラフィックスはあったほうが安心です」とだけは言っておきます。
必ずオンボードグラフィックスがあるもの(マザーボード)を選べとは言いませんが、頭の片隅に記憶しておいてください。
メモリはできれば64GB以上、少なくとも32GBは欲しい
上でも触れましたが、メモリは64GB以上は欲しいところです。
ゲーミングPCと3DCGなどのクリエイティブ用途のPCとの一番の差は必要とされるメモリの容量になります。
目安としてはゲーミングPCや一般的なPCで◯◯GB以上欲しいと言われている倍は欲しいと思っておいてください。
今(2025年)の風潮だとPCのメモリは32GBは欲しいという声が増えてきています。よってクリエイティブ用途のPCでは64GBは欲しいです。もちろん予算がある人は128GBのほうがベターなのは言うまでもありません(128GBあればより長く使えるでしょう)。
とはいえ、メモリを64GBにするとコストが跳ね上がってしまうので、最低32GBのラインは死守したいところです。
しかし、金銭的にどうしても厳しい場合は16GBでも3DCGをやるためのPCを用意してください。その場合はあとからメモリを増設できるように空きスロットを用意しておきましょう(安価なPCで3DCGをはじめる場合はコスト重視で割り切ることも大事です)。
3DCG向けのPCにおけるパーツの優先順位【Maya, Blender, Unreal Engine】
3DCG用のBTOパソコンを選ぶ上で優先すべき順位は次のとおりです。
グラフィックカード(GPU) > CPU > メモリ > ストレージ
実際にBTOパソコンを選ぶ際は最初にCPU(チップセット)から選びます(intel or AMD)。そういった意味ではCPUが一番大事ですが、CPUよりもGPUに費用をかけるべきなのでこの順位としました。
2024年12月現在。intelの13世代と14世代CPUの主にKつきモデルと呼ばれるハイエンドCPUに不具合、または劣化と言われる問題が発生しています。
この問題を回避するためにはBIOSを変更してCPUのクロックを下げることになるのですが、そうするとKつきモデルの本来のパフォーマンスから大幅に下がった性能しか発揮できなくなってしまいます(壊れるよりは良いですが…)。
intelによると「0x12B」というマイクロコードを適用することでこの不具合問題は解決するとのことですが、
何を言っているかよくわからない初心者の方がintelのCPUを購入することはおすすめしていません。
CPUとメモリの順位に関してはメモリはあとから増設することが比較的簡単ですが、CPUの交換は簡単なものではないのでこの順位にしました。予算が厳しい場合はメモリはあとから増設することを想定してスロットを開けておきましょう。
ストレージに関しては、起動ドライブを交換するのはなにかと面倒で、メモリを増設するほうが楽です。しかし、この順位としました。
- 【グラフィックカード(GPU)】 NVIDIA GeForce RTX 5000番台(安くても古い世代のものは避けたい)。
- 【CPU】intelならばcore Ultra 7以上、AMDならばRyzen 7以上(GPUほどではないが、新しい世代のほうが好ましい)。
- 【メモリ】可能ならば64GB以上(少なくとも32GB以上は欲しい)。
- 【ストレージ(SSD)】起動ディスク(Cドライブ)は、できればm.2のNVMe接続のもの。1TB(最低でも512GB)は欲しい。2TBならばなお良し(起動ドライブの空き容量不足は動作が不安定になるため余裕がほしい)。
優先順位が上の通りだからといって、GeForce RTX 5090にcore i3のCPUに8GBのメモリで、起動ドライブに256GBのSSDといった偏った一点豪華主義(そういう人はいないと思いますが…)のような構成はいけません。
それぞれのバランスを考えた上で、コストを削減する場合はグラフィックカードのランクを下げるのが現実的です。グラフィックカードを交換するのはそれほど難しくないからです。
ストレージを節約したい場合は起動ディスクはある程度きちんとしたものにして、データドライブを安くすませる、または、なくす(後で増設する)ようにしましょう。
おすすめのBTOパソコン【Maya, Blender, Unreal Engine】
BTOパソコンでおすすめのものをいくつかピックアップしておきます。
上に書いた内容を理解した上で、予算に応じてカスタマイズしてください。
マウスコンピューター
「パソコン買う、ならまずマウス。」ということで、まずはマウスコンピューターから紹介します。
マウスコンピューターの最大のウリは、「標準無償保証期間が3年」ということです。
ほかのBTOメーカーでは保証期間1年が標準で、オプションで追加料金を払えば2年、3年と延長することが出来ます。しかし、マウスコンピューターは「標準無償保証期間が3年」なので購入後の心配がありません。初心者から上級者まですべての人が受けられる素晴らしい恩恵です。
そして、マウスコンピューターにはDAIVというクリエイターパソコンのブランドがあります。
そのDAIVシリーズには、「NVIDIA STUDIO 認定PC」というものがあります。
よくわからない場合には、「NVIDIA STUDIO 認定PCのDAIVのパソコンを選んで置けば間違いない」です。
3DCGの制作現場においてもよく使用されている安心のブランドです。
マウスコンピューターは店舗数が少なく、国内の工場で組み立てているのでコスパにも優れています。
さらに、BTOパソコンで有名な大手ということで安心感もあります。
トータルで考えると一番のオススメです。
DAIV KM-I7G7T(NVIDIA Studio 認定PC)(オータムセール 20,000円 OFF(2025/10/08 11:00~2025/10/29 10:59))
| DAIV KM-I7G7T(NVIDIA Studio 認定PC) | ||
|---|---|---|
| デフォルト構成 | おすすめ構成 | |
| OS | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Pro 64bit |
| CPU | インテル(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサー 265 (20コア / 8 P-cores / 12 E-cores / 20スレッド / 最大5.3GHz / 30MB) | インテル(R) Core(TM) Ultra 9 プロセッサー 285 (24コア / 8 P-cores / 16 E-cores / 24スレッド / 最大5.6GHz / 36MB) |
| CPUクーラー | 水冷CPUクーラー (240mm長の大型ラジエーターで強力冷却) ※ケースファン3個以上と組み合わせください | 水冷CPUクーラー (240mm長の大型ラジエーターで強力冷却)※ケースファン3個以上と組み合わせください |
| MB | インテル(R) B860 チップセット ( MATX / SATA 6Gbps 対応ポートx4 / M.2スロットx2 ) | インテル(R) B860 チップセット ( MATX / SATA 6Gbps 対応ポートx4 / M.2スロットx2 ) |
| グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti / 16GB ( DisplayPort×3 / HDMI×1 ) | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti / 16GB ( DisplayPort×3 / HDMI×1 ) |
| メモリ | 32GB メモリ [ 16GB×2 ( DDR5-5200 ) / デュアルチャネル ] | 32GB メモリ [ 16GB×2 ( DDR5-5200 ) / デュアルチャネル ] |
| M.2 SSD(1st) | 2TB NVMe SSD ( M.2 PCIe Gen4 x4 接続 ) | 2TB NVMe SSD ( M.2 PCIe Gen4 x4 接続 ) |
| M.2 SSD(2nd) | なし | 1TB NVMe SSD ( M.2 PCIe Gen4 x4 接続 ) |
| 電源 | 850W 電源 ( 80PLUS(R) GOLD ) | 850W 電源 ( 80PLUS(R) GOLD ) |
| 価格 | 389,800円(2025/10/11現在) | 451,400円(2025/10/11現在) |
標準構成で389,800円(2025/10/11現在)です。
ですが、おすすめの構成にカスタマイズしたものが一番のおすすめになります。
intel Core Ultra 9 285K プロセッサーにアップグレードした、NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti を搭載したこちらのモデルです。コスパに優れた高性能モデルです。
ポイントは、CPUをCore Ultra 9 285Kにアップグレードすることで、大幅に性能をアップさせられるところです。
こちらの構成が、451,400円(2025/10/11現在)です。
予算が許すならば、「一番おすすめ」です。
今、オータムセール 20,000円 OFF(2025/10/08 11:00~2025/10/29 10:59)なので、購入するチャンスです。
また、パソコン下取りサービスを利用すると、1,100円OFFになるので、利用できる方は忘れずに。
しかし、もう少し予算を出せるならば「DAIV FM-A7G80」のほうをおすすめします。
こちらは、GeForce RTX 5080 を搭載したハイエンド構成です。
さらに、最上級のGeForce RTX 5090を搭載したものが欲しければ「DAIV FX-I9G90 (NVIDIA Studio 認定PC)」または、「
DAIV FM-A9G90」をどうぞ。
ほかにもマウスコンピューターのPCを知りたい場合は「3DCGをはじめるならこれを買え!《PC編》」の記事を読んでください。予算別におすすめPCを紹介しています。こちらの構成よりも安価なものも提案していますので、参考にしてみてください。
G TUNE DG-A7G6T(オータムセール 30,000円 OFF(2025/10/08 11:00~2025/10/29 10:59) )
そうはいっても、「40万円台は高い…」という方のために、20万円台のおすすめも紹介しておきます。
こちらは、クリエイター向けのDAIVではない、「G-Tune」というゲーミングPCのブランドです。
現在、オータムセール 30,000円 OFF(2025/10/08 11:00~2025/10/29 10:59)です。
| G TUNE DG-A7G6T | ||
|---|---|---|
| デフォルト構成 | おすすめ構成 | |
| OS | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Pro 64bit |
| CPU | AMD Ryzen 7 5700X プロセッサ ( 8コア / 16スレッド / 3.4GHz / 最大4.6GHz / L3キャッシュ32MB ) | AMD Ryzen 7 5700X プロセッサ ( 8コア / 16スレッド / 3.4GHz / 最大4.6GHz / L3キャッシュ32MB ) |
| CPUクーラー | 水冷CPUクーラー (240mm長の大型ラジエーターで強力冷却) | 水冷CPUクーラー (240mm長の大型ラジエーターで強力冷却) |
| MB | AMD B550 チップセット ( Micro ATX / DDR4 / SATA 6Gbps 対応ポート×5 / M.2スロット×2 ) | AMD B550 チップセット ( Micro ATX / DDR4 / SATA 6Gbps 対応ポート×5 / M.2スロット×2 ) |
| グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX 5060Ti / 16GB ( DisplayPort×3 / HDMI×1 ) | NVIDIA GeForce RTX 5060Ti / 16GB ( DisplayPort×3 / HDMI×1 ) |
| メモリ | 32GB メモリ [ 16GB×2 ( DDR5-5600 ) / デュアルチャネル ] | 32GB メモリ [ 16GB×2 ( DDR5-5600 ) / デュアルチャネル ] |
| M.2 SSD | 1TB NVMe SSD ( M.2 PCIe Gen4 x4 接続 ) | 1TB NVMe SSD ( M.2 PCIe Gen4 x4 接続 ) |
| 電源 | 750W 電源 ( 80PLUS(R) BRONZE ) | 750W 電源 ( 80PLUS(R) Gold ) |
| 価格 | 219,800円(2025/10/11現在) | 234,100円(2025/10/11現在) |
こちらは、CPUは「AMD Ryzen 7 5700X」と、GPUは「NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti(16GB)」の組み合わせです。CPUこそ1世代前のものとなりますが、GPUメモリが16GBもある非常にコスパが良いおすすめモデルになっています。
デフォルトの構成は、219,800円(2025/10/11現在)です。
しかし、OSをWindows 11 Proに変更し、念のため電源もアップグレードした、234,100円(2025/9/26現在)がおすすめです。
これは、私が過去にPCで電源のトラブルに見舞われたことがあるので、念のためにアップグレードをおすすめしています。5000円くらいで安心を買えるなら買っておきたいと考えたためです。
したがって、私のような心配性ではない人には、電源をアップグレードする必要はありません。
もう少し予算が出せる人は、SSDをより大容量のものにアップグレードするか、データ用のHDDを追加すれば、使い勝手が大幅に良くなります。
現在、オータムセール 30,000円 OFF(2025/10/08 11:00~2025/10/29 10:59)なので、アップグレードするチャンスです。
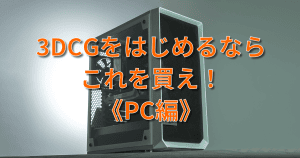
FRONTIER
FRONTIERはコスパに優れたBTOパソコンメーカーです。
とにかく安く3DCGをはじめたい方には超おすすめです。
そうしたFRONTIERで安価なPCをお探しの方は、こちらでスペックについて詳しく紹介しているので、カスタマイズの際の参考にしてください。
クリエイター向けのCR seriesという新しいラインナップが追加されました。
FRCRB650/CG3
コスパに優れたFRONTIERということで、思い切ってGeForce RTX 5090のPCを見てみましょう。
クリエイター向けのCR seriesの中から、「AMD Ryzen 9 9950X3D プロセッサー」と「NVIDIA GeForce RTX 5090」という構成の「
FRCRB650/CG3
」を紹介します。
| FRCRB650/CG3 | ||
|---|---|---|
| デフォルト構成 | おすすめ構成 | |
| OS | Windows 11 Home 64bit版 [正規版] | Windows(R) 11 Pro 64bit版[正規版] |
| CPU | AMD Ryzen 9 9950X3D プロセッサー (4.3GHz[P-core][最大5.7Ghz]/16コア/32スレッド/128MB L3キャッシュ/TDP 170W) | AMD Ryzen 9 9950X3D プロセッサー (4.3GHz[P-core][最大5.7Ghz]/16コア/32スレッド/128MB L3キャッシュ/TDP 170W) |
| CPUクーラー | 【MSI製】水冷CPUクーラー【MAG CORELIQUID I360 / 冷却ファン3基】 | 【MSI製】水冷CPUクーラー【MAG CORELIQUID I360 / 冷却ファン3基】 |
| CPUグリス | 標準CPUグリス | CWTP-EG4GUR えくすとりーむ 4G あるてぃめいと |
| MB | ASRock B650 Pro RS(ATX / Wi-Fi非搭載) | ASRock B650 Pro RS(ATX / Wi-Fi非搭載) |
| グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB【HDMI x1/ DisplayPort x3】 | NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB【HDMI x1/ DisplayPort x3】 |
| メモリ | 64GB (32GB x2) PC5-44800 (DDR5-5600) DDR5 SDRAM DIMM | 128GB (32GB x4) PC5-44800 (DDR5-5600) DDR5 SDRAM DIMM |
| M.2 SSD(1st) | 2TB WD BLACK SN850X(読出7300MB/s,書込6600MB/s) | 2TB SSD |
| M.2 SSD(2nd) | なし | 【NVMe SSD PCIe4.0】2TB Crucial製 |
| 電源 | 【静音電源】1500W ATX 3.1電源 80PLUS PLATINUM(日本製コンデンサ仕様) | 【静音電源】1500W ATX 3.1電源 80PLUS PLATINUM(日本製コンデンサ仕様) |
| 送料 | 3,300円(税込み) | 3,300円(税込み) |
| 価格 | 818,100円(2025/10/11現在) | 888,500円(2025/10/11現在) |
標準構成で818,100円(2025/10/11現在)です。
正直な話、Windows 11 Pro にアップグレードした、826,900円(2025/10/11現在)でも良いでしょう。
しかし、これほどのハイエンドの構成ならば、あとから後悔しないように、しっかりとアップグレードをしておきましょう。
おすすめは、OSをWindows11 Proに、そして、メモリを128GBまで積み、2ndのSSDを2TBまで積み、CPUグリスまでアップグレードした、888,500円(2025/10/11現在)です。
最強のものが欲しい方は、ぜひ検討してみましょう。
FRGHLMB650/M901
「AMD Ryzen 7 9700X プロセッサー」と「NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti」という非常にバランスの取れたコスパ重視の構成です。
| FRGHLMB650/M901 | ||
|---|---|---|
| デフォルト構成 | おすすめ構成 | |
| OS | Windows 11 Home 64bit版 [正規版] | Windows(R) 11 Pro 64bit版[正規版] |
| CPU | AMD Ryzen 7 9700X プロセッサー(3.8GHz[最大5.5GHz]/8コア/16スレッド/32MB L3キャッシュ/TDP 65W) | AMD Ryzen 7 9700X プロセッサー(3.8GHz[最大5.5GHz]/8コア/16スレッド/32MB L3キャッシュ/TDP 65W) |
| CPUクーラー | CPS サイドフローCPUクーラー【RT400-BK】 | CPS サイドフローCPUクーラー【RT400-BK】 |
| CPUグリス | 標準CPUグリス | 標準CPUグリス |
| MB | MSI B650 GAMING PLUS WIFI(ATX / Wi-Fi搭載) | MSI B650 GAMING PLUS WIFI(ATX / Wi-Fi搭載) |
| グラフィックス | 【MSI製】NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16GB【HDMI x1/ DisplayPort x3】 | 【MSI製】NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16GB【HDMI x1/ DisplayPort x3】 |
| メモリ | 32GB (16GB x 2) PC5-44800 (DDR5-5600) DDR5 SDRAM DIMM | 32GB (16GB x 2) PC5-44800 (DDR5-5600) DDR5 SDRAM DIMM |
| M.2 SSD(1st) | 【NVMe SSD PCIe4.0】2TB Crucial製 | 【NVMe SSD PCIe4.0】2TB Crucial製 |
| M.2 SSD(2nd | なし | 【NVMe SSD PCIe4.0】1TB Crucial製 |
| 電源 | 850W ATX 3.1電源 80PLUS PLATINUM(日本製コンデンサ仕様) | 850W ATX 3.1電源 80PLUS PLATINUM(日本製コンデンサ仕様) |
| 送料 | 3,300円(税込み) | 3,300円(税込み) |
| 価格 | 286,100円(2025/10/11現在) | 308,100円(2025/10/11現在) |
デフォルトの構成で、286,100円(2025/10/11現在)ですが、Windows 11 Proにアップグレードした、294,900円(2025/10/11現在)からのスタートにしましょう。
したがって、おすすめの構成は、Win11 Pro、2ndのSSDも1TB増設し、さらに、CPUクーラーとCPUグリス、そして電源までアップグレードした、300,100円(2025/10/11現在)です。
@Sycom(サイコム)
サイコムはPCに詳しい人におすすめです。
マザーボード、グラフィックカード、電源、CPUクーラーといったものまで、具体的な製品名から選ぶことが出来ます。パーツ1つ1つの細部にまでこだわりたい人には、たまりません。
ただし、逆に言えば、PCに詳しくない人にとっては選択肢が多すぎるので、何を選んだらよいのかわからなくなってしまうかもしれません。
PCに詳しい人は、ここまでの話を参考にパーツ選びをして、サイコムのBTOを検討してみましょう。
サイコムのおすすめは、AMDのCPUモデルの「Premium Line X870FD-A」です。
AMDのCPUモデルです。
「Premium Line」のPCは、標準で2年保証がつき、無償オーバーホール(内部クリーニング、CPUグリスの塗り直し、BIOSやドライバの更新、動作確認)を行ってくれます。特に、CPUグリスの塗り直しまでしてくれるところは他に知りません。
また、アップグレードサービスでは、パーツ増設の際のアップグレードに関する相談を受けてくれて、その際のパーツ取付サービスとパーツ下取りサービスがあります。
古くなったら新しいものに買い替えるのではなく、自作PCのようにパーツを入れ替えて末永く使い続けることが出来ます。
この「Premium Line」のモデルならば購入後も安心です。
AMDのCPUのほうが、CPUソケットの互換性維持期間が長いので、「Premium Line X870FD-A」をおすすめとして挙げました。
しかし、intelのCPUの「Premium Line Z890FD」が、ダメなわけではありません。
両方のPCで構成を組んでみたうえで、検討することを強くおすすめします。
ちなみに私は、このサイコムの「Premium Line」のPCを愛用しています。
参考になるかどうかわかりませんが、私が購入したものは、Ryzen9950X3DとGeForce RTX 5090の構成のものです。
高価ですが、パーツを1つ1つしっかり選んで購入したい。そして、パーツを交換して末永く使いたい場合には、非常におすすめです!
「Premium Line B650FD-Mini/T/A」というおしゃれでコンパクトなモデルもありますが、性能的に上限が低いのと、拡張性を考えるとミドルタワーのものをおすすめします。
また、サイコムは「水冷パソコンのサイコム」としても有名で、サイコムオリジナルの水冷システムは定評があります(サイコム独自技術によるハイエンドビデオカードの水冷化によるCPUとGPUのデュアル水冷システムが有名です)。
まとめ
トータルで考えると大手で保証期間が3年もある「マウスコンピューター」の私がおすすめしたPCを選んでおけば間違いありません。
「FRONTIER」はコスパが良いので、非常にバランスの良いAMD Ryzen 7 9700XとGeForce RTX 5070 Ti搭載の「
FRGHLMB650/M901」
。
または、思い切って、CG用のマシンの最強構成であるAMD Ryzen 7 9950X3DとGeForce RTX 5090搭載の「
FRCRB650/CG3
」にしましょう。GeForce RTX 5090搭載のPCも発売当初に比べて、だいぶ購入しやすくなってきました。検討してみても良いでしょう。
パーツを交換しながら末永く1台のPCとお付き合いしたい場合はサイコムの「Premium Line」の「X670FD-A(AMD)」がおすすめです。
上記3つのショップから購入する場合は、迷うことなくすぐに3DCGの世界へ行くことが出来るでしょう。
とにかく安いPCで3DCGをはじめたい人へ
ここでは、これから3DCGをはじめる人に向けて、安価なマシンを2つピックアップしておきます。
購入される場合はなるべく早く決断してください。
グラフィックカードは使うモニターの解像度によってパワーとメモリを必要とします。
フルHDのモニター1つ(2枚くらいいけるでしょう…)ならばMayaやBlenderは当然のことながらUnreal Engineも動かして勉強するくらいなら可能です。
まず、1つめは、マウスコンピューターのPC「NEXTGEAR JG-A7G6T」です。
FRMFGB550/M904

2つ目が「
FRMFGB550/M904」です。
こちらは、GPUが「NVIDIA GeForce RTX 5060Ti(8GB)」ですが、嬉しいことに、16GBにアップグレードも可能です!。
とにかく安く購入したい場合は、デフォルトのRTX 5060Ti(8GB)のままにすることで、価格をおさえることができます。しかし、できることならば、RTX 5060Ti(16GB)にアップグレードして購入したいところです。
※保証を重視したい場合は、標準で3年保証のマウスコンピューターがおすすめです。
| FRMFGB550/M904 | ||
|---|---|---|
| デフォルト構成 | おすすめ構成 | |
| OS | Windows 11(R) Home 64bit版 [正規版] | Windows(R) 11 Pro 64bit版[正規版] |
| CPU | AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー(3.4GHz[最大4.6GHz]/8コア/16スレッド/32MB L3キャッシュ / TDP 65W) | AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー(3.4GHz[最大4.6GHz]/8コア/16スレッド/32MB L3キャッシュ / TDP 65W) |
| MB | MSI MPG B550M GAMING PLUS(ATX) | MSI MPG B550M GAMING PLUS(ATX) |
| グラフィックス | 【MSI RTX5060Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS】GeForce RTX 5060 Ti 8GB【HDMI x1 / DisplayPort x3】 | 【MSI RTX5060Ti 16G SHADOW 2X OC PLUS】GeForce RTX 5060 Ti 16GB【HDMI x1 / DisplayPort x3】 |
| メモリ | 32GB (16GB×2) PC4-25600 (DDR4-3200) DDR4 SDRAM DIMM | 32GB (16GB×2) PC4-25600 (DDR4-3200) DDR4 SDRAM DIMM |
| M.2 SSD(1st) | 【MSI製】1TB SPATIUM M470 PRO(読出6000MB/s,書込4500MB/s) | 【MSI製】1TB SPATIUM M470 PRO(読出6000MB/s,書込4500MB/s) |
| M.2 SSD(2nd) | なし | なし |
| 電源 | 600W ATX電源 80PLUS PLATINUM(日本製コンデンサ仕様) | 600W ATX電源 80PLUS PLATINUM(日本製コンデンサ仕様) |
| 送料 | 3,300円(税込み) | 3,300円(税込み) |
| 価格 | 170,100円(2025/10/11現在) | 193,200円(2025/10/11現在) |
標準構成で170,100円(2025/10/11現在)です。
おすすめは、Windows 11 Proに変更し、GPUをGeForce RTX 5060 Ti(16GB)にした、193,200円(2025/10/11現在)の構成です。
特にVRAMが8GBから16GBになる違いは非常に大きいので、GPUは、ぜひともアップグレードしておきたいところです。
なんとか20万円以内におさめることができました。
しかし、もう少し予算が出せる人は、データ用の2ndのSSDを追加すると、使い勝手が良くなります。
10万円台のPCで3DCGを始めるならば超おすすめです。
どうしても決められないあなたへ
いろいろ紹介して盛りだくさんの記事になってしまったので、決められない人も多いかと思います。
そうしたあなたのために、予算別に3DCG用PCを具体的にセレクトした記事を書きました。
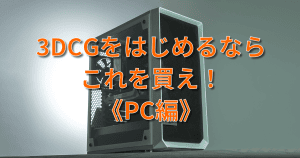
最後に
3DCG用のPCを手に入れたら「3DCGのはじめかた」を読んでください。
具体的に3DCGをはじめる方法を解説(3DCGソフトは何を使えばよいのか?3DCGソフトをはじめたばかりの時は、どうやって学んでいけばよいのか?等)しています。
具体的には「3DCGソフトは何を使えばよいのか?」「3DCGソフトをはじめたばかりの時は、どうやって学んでいけばよいのか?」等が書かれています。

具体的にMaya(3DCG)を学び始める段階にきたら、以下のロードマップを参考にすると効率良く学習を進めることができます。

すばらしい3DCGライフを!


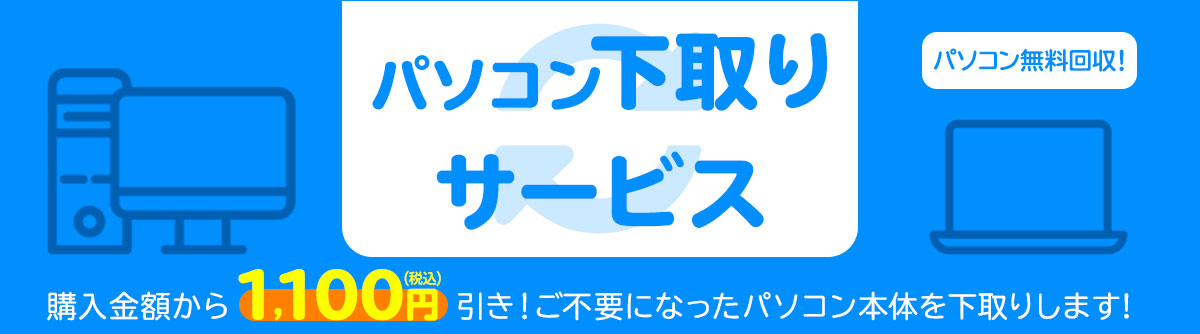





コメント