「初心者、未経験者のための3DCGソフト選び」の結論はから述べると
「Maya」か「Blender」のどちらか(または両方)です。
もちろんそれ以外にも素晴らしい3DCGソフトウェアはあります。
しかし、最初に触れた3DCGソフトウェアというものは良くも悪くも後々まで影響を残すものです。
ちなみに私が最初に触れた3DCGソフトウェアはLightWaveです。
しかし、今ではすっかりMaya派です。もう20年近くMayaを使用しています。
そういう私は完全にMaya派の人間ではありますが、BlenderとHoudiniには強い関心を持っています。
私が3DCGを学び始めた頃と今では3DCGソフトウェアのシェア等の状況が様変わりしています。当時非常によく使われていた某有名3DCGソフトウェアが今は存在しません。良くも悪くも時代の移り変わりが早いのがこの3DCG業界です。その荒波に備えるためにも2025年現在の3DCGソフトウェア選びを考えてみたいと思います。
具体的にいくつかのソフトウェアを検証してみますが、初心者、未経験者向けなのであまり専門的な内容にまでは触れませんので気軽に読んでみてください。
また、ソフトウェアではなくハードウェア(3DCG向けのPC)の選び方についてはこちらの記事を御覧ください。

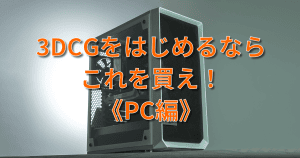

実際に3DCGを学習したくなったらこちらの記事をどうぞ。


Maya or Blender どっち?
2025年現在の統合3DCGソフトウェア選びは、上で述べたように「Maya」か「Blender」の2択です。
ではどちらを選ぶべきかは条件次第だと考えます。
その条件とは「プロとして仕事として3DCGをやりたいか否か?」です。
プロ志向の方はMayaがベストです。Mayaは業界標準ツールであり、ハリウッド映画やビデオゲームなど3DCGが使われる制作現場ではMayaは使えて当たり前の状況が出来上がっています。
もう一つの条件は「学生か否か?」です。
学生ならばMayaは無料で使用できますので今の所仕事としてやりたいと考えていないとしてもこの学生特権を利用しない手はありません。
つまりそれ以外の方はBlenderをおすすめします。
とはいえ、Blenderも様々なところで使用例が増えてきています。
個人で映像作家としてやりたいのであればBlenderもおすすめします。
しかし、大手ゲームや映画等の大人数のプロジェクトで働きたい場合はMayaをおすすめします。
Mayaの特徴
Mayaの特徴
- 業界標準のツールである。
- 大規模開発プロジェクトに向いている。
- 有料(サブスクリプションは高額)。
Mayaの特徴は業界標準であるためユーザー数が多く、情報が出回っています。このブログも3DCGについてはほぼMayaについての情報を扱っています。
ただ、欠点としては学生以外の場合は価格が非常に高い(オートデスクのサブスクリプションのページへのリンクです)ということです。趣味でやるにはそうとう高価なものになると思います。
Mayaにインディー版が登場しました。これによって学生でなくても個人でMayaを導入しやすくなりました。いろいろ条件があるようですが、個人で学ぶためならばこれらの条件はあまり関係ないでしょう。
ただ仕事として3DCGをやりたいとなると専門学校で学ぶという選択肢もあります。 学生版が使える条件を満たすような Mayaを学べる3DCGの専門学校等を探してみてください。
もし、今学生の方は、色々と登録するのが面倒かもしれませんがMayaの学生版を使ってみてください。


Blenderの特徴
Blenderの特徴
- 無料で使用できる。
- 勢いがあって活気がある。
- アドオンが非常に豊富。
- 大規模プロジェクトには向かない。
Blenderは現状でもっとも勢いのある3DCGソフトウェアです。しかも完全に無料で使えます。
以前はインターフェイスが独特ですでに3DCGをやっている人々からは使いにくいと言われています(初めての3DCGソフトウェアの場合は関係無いでしょう)。ものすごいスピードでバージョンアップされていて、4.0がリリースされました。もっとも勢いがありダイナミックさを体感することができます(昔はMayaのバージョンアップの度に心を踊らせていましたが、今のMayaには心躍らされることはほとんどありません…)。
とにかく今すぐ3DCGを始めたいという方にはBlenderを今すぐ使い始めることをおすすめします(Mayaの学生版のような面倒な登録作業がない)。が、仕事として3DCGをやりたいと思っている方は現状では必ずMayaを使えるようにならなければいけないので学習の二度手間になってしまう可能性があります。ただ、3DCGを実際に体験してみて自分に適正があるかどうかを試すためにもBlenderは最善の選択(学生の場合はいきなりMayaで問題ないと思います)だと言えます。
また、BlenderはMacで3DCGをやってみたい場合はベストな選択肢の1つです。
Apple Siliconにネイティブに対応し、MetalでのGPUレンダリングにも対応しています。BlenderはApple Siliconの有り余るパワーを最大限に発揮してくれる稀有な存在です。
その他の3DCGソフトウェア
当然ながら3DCGソフトウェアはMayaとBlenderだけではありません。
この記事では基本的には統合型の3DCGソフトウェア(モデリングからアニメーション、レンダリングまで一通り出来るもの)を扱っていますが、フィギュアを3Dプリントしてみたいとかとにかくモデリングがしたい等目的がはっきりとしている場合は例外的にZBrushをおすすめします。
ZBrush
ZBrushとはスカルプティング(彫刻)でモデルを作るモデリングに特化したソフトウェアです。
特に人間や動物、クリーチャー等有機体(生き物)をモデリングするのに適しています。
基本的にはモデリングしか出来ないのですが、とにかくデジタルスカルプチャーでものを作りたいという方にはいきなりZBrushで良いのではないでしょうか。統合型の機能をいちいち覚えていくよりもやりたいことが決まっていてすぐに取り掛かりたいという方には特におすすめです。
SculptrisというZBrushの無料版ともいうべきソフトウェアがあるのでまずはこちらでためしてみてください。まず無料で試して自分の適性を探る。これ大事です。
3ds Max
3ds MaxはMayaと同じAutodeskが提供する3DCGソフトウェアです。Autodeskには主にゲーム業界で使われていたSomftimage(XSI)というソフトウェアも提供していましたが、開発中止になってしまいました。1社で3つも統合型3DCGソフトウェアを持っていた状態から現在のMayaと3ds Maxの2つになりました。先に述べたようにMayaは業界標準ツールとしての地位を築いています。そこで将来性を考えると3ds Maxを積極的に選ぶ理由はないと判断しました。
3ds Maxは日本ではアニメ業界でよく使用されています。それはPencil+というセル画のように表現できるプラグインが非常に高く評価されているためです。あの 『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』 シリーズで使われていることで有名です。また、ゲーム業界ではアサシンクリードシリーズ(Ubisoft)やダークソウルシリーズ(フロム・ソフトウェア)等で使われていたことで有名です。
少し前までならアニメなら3ds Maxという選択肢もあったかもしれません。しかし、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』の制作会社カラーがBlender財団に賛同、開発資金の提供を含めて協力することが発表され、2020年公開予定の新作の一部にもBlenderが使われるということが大きなニュースになりました。また、Ubisoftアニメ部門ではBlenderを採用するというニュースも話題になりました。
ただ、3ds Maxは建築関係に力を入れているようですが、私はそちら方面は全くわからないのでコメントできません。すでに今の会社で使っているから勉強したい等の明確な理由があれば全く別問題です。
Houdini
Houdiniは完全プロシージャルなノードベースのワークフローを売りにしています。しかし、初心者、未経験者にとっては何を言っているのか全く意味がわからないと思います。よって、初心者、未経験者向けではないという理由でここではおすすめしません。
エフェクトをやりたい人は最初からHoudiniで良いのかもしれませんが、MayaやBlenderに比べて圧倒的に情報が少ないので、おすすめはできません。私自身もHoundiniを触ったことがないのでなおさらです。
とにかく高度なエフェクトはこのHoudiniで作られたものが多いです。
エフェクトの分野では他の3DCGソフトウェアからHoudiniへの移行が進みつつあります。現状では他の3DCGソフトウェアを使用した場合実現するのが難しい(非常に手間がかかる等)場合に登場するようなソフトウェアです。使いこなせるようになれば大きなアドバンテージを得ることが出来るでしょう。Houdiniについては初心者、未経験者にとってはそのようなイメージを持つだけで今のところは十分だと思います。
初心者は「高度なエフェクトを見たらHoudiniだと思え!」でとりあえず十分です。
Houdiniは情報が少なく学びにくかったのですが、初心者向けの本が出版されたので学習しやすい環境が整ってきました。
実は私もこの2冊を購入しました。
最初に読むのは『挫折させないHoudiniドリル』の方をおすすめします。
Cinema 4D
Cinema 4DはAfterEffectsとの連携に強いソフトウェアです。というよりそれ以外のことは私はよく知りません。モーショングラフィックスに強いようですが、私はそちら方面のことはよくわかりません。よってAfterEffectsが得意でその特技を活かしたい人向けです。よって、このような明確な使用目的がなく漠然と3DCGをやりたいと思っている人には強くおすすめする理由はありません。
LightWave
LightWaveについて私は主にモデリングで一部こだわりのあるユーザーに支持をされているという印象を持っています。よって初心者、未経験者の方たちはまだこだわりはないはずなので積極的に選ぶ理由はないと考えました。
「Unreal Engine」という第3の道
「Maya」か「Blender」か?
ではなく、第3の道として「Unreal Engine」を紹介します。
「Unreal Engine」はゲームを作るためのゲームエンジンですが、豊富な高クオリティーアセットを使用して3DCG動画を効率よく作成することが出来ます。
統合型の3DCGツール(DCCツール)を学ぼうとすると、どうしてもモデリングからのスタートになってしまい、その段階で脱落してしまう人が多々います。3DCGではモデリングだけでなく、レイアウト、アニメーション、リギング、ライティング、エフェクト等様々な工程があります。それらの工程のどこに自分が面白さを感じるかというのは人それぞれで適性も違っています。「Unreal Engine」で動画作成することによって、レイアウト、環境構築(背景、ステージ作成)、ライティング、カメラワークなどをすぐに経験することが出来ます。これらの工程は3DCGでも特に人気があり、面白い分野でもあるので、そこから経験できるというのは非常に大きいです。
というわけでまずは、「Unreal Engine」で3DCGのどの部分に自分が面白く感じて適性があるのか?というのを探るのが一番良い方法なのではないかと思います。そこで自分の適正を確認してから「Maya」か「Blender」か?という段階に移行することを強くおすすめします。そうすればモデリングが得意でなくてもそこで挫折することなく自分の適正のある分野まで学習を進める確率があがっているはずです。
「Unreal Engine」についてはUdemyで受けた講座のレビュー記事がありますので、よかったら参考に読んでみてください。

結論
最後にもう一度結論です。
学生ならばMaya(Blenderでも良いが学生特権を使うべき)
なんらかの形で3DCGの仕事をしたいと考えている場合は、Mayaがベターです。
完全に趣味でやりたい。面倒な登録作業をせずにすぐに始めたい場合は、Blenderがおすすめです。
とにかく造形したいならばいきなりZBrushもありです。
です。
上で仕事をしたいならMayaと書きましたが、ポートフォリオ(作品)が良ければ、Blenderでも、Mayaでもそれ以外のアプリケーションでも十分にチャンスはあります。MayaかBlenderかで迷っている暇があったら、少しでも早く始めて自分で作品を作れるようになりましょう。
また、Mayaを習得して仕事をしたいといった場合には専門学校を利用するのも有用です。たしかに学費はかかりますが、時間的には効率よく学習をすすめることができます。また、わからないことをすぐ聞くことができるというメリットもあります。専門学校ならば就職の支援もしてくれるでしょう。
私はデジハリ(オンラインではない)に通っていました。今ではオンラインでどこに住んでいても授業を受けることができるようになりました。不明点があれば個別相談会で聞かれてみてはいかがでしょうか。


BlenderにしろMayaにしろ始めるにはPCが必要です。
「どういったPCを選べばよいのか」については以下の記事を御覧ください。

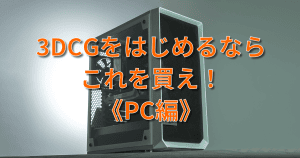






コメント